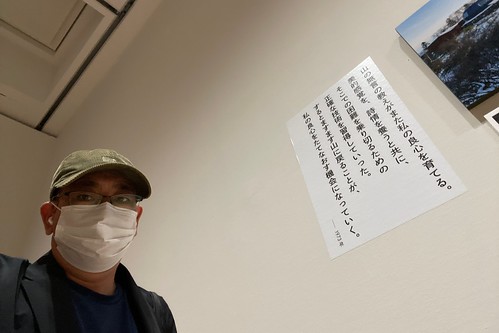|
| プロフィール |
| 藤本寿徳 |
| ← | 2024年7月 | → | |||||
| S | M | T | W | T | F | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 最近の記事 |
| 新刊のお知らせ-「建築・住宅デザ ..
|
| 新刊のお知らせ-「建築・住宅デザインの現場」 |
|
新刊「建築・住宅デザインの現場」に 「向洋の家」や螺旋階段を掲載していただきました。 8組の建築家の住宅設計の考え方が紹介されている美しい本です Amazonのリンクをシェアさせていただきます。 ぜひお買い求めください。 Amazonで見る 建築にとって「詩的な空間」「情緒的な空間」というのが一番の価値だと思っています。 それが大事だと言う本は今までも多々あるのですが(抽象的な議論になると哲学的で難解なものも多い)「詩的な」「情緒的な」と言うのは受け手側の感想であり、建築ができた後の結果です。 設計者にとって大事なのは、それを如何に作るかであって、大学教育でもその方法論を授業で教えることは短い時間では難しい事です。 一般の人にとっても建築のリテラシーを高める必須のテーマです。 この本はその方法論を一般の人にも伝えようという編集者のチャレンジなのだと思います。 今後もいろんな建築家を取り上げシリーズ化していって欲しいです。 この本では「詩的な空間」「情緒的な空間」をメインに捉えている建築家ばかりで、その中に選ばれたことは名誉なことだと感じています。読後の感想ですが、建築って楽しいなと幸せな気持ちになりました。 「建築・住宅デザインの現場」 著者について 高野保光/芦沢啓治/新関謙一郎/手嶋保/藤本寿徳/熊澤安子/杉下均+出口佳子/中山大介 出版社 グラフィック社 発売日 2024/7/8 単行本(ソフトカバー)224ページ  |
10:45, Wednesday, Jul 10, 2024 ¦ 固定リンク
| アスタリスクのミニムービー |
|
ミニムービーをyoutubeにアップしました |
09:52, Tuesday, Mar 19, 2024 ¦ 固定リンク
| 大山6合目避難小屋の美しさ |
09:24, Saturday, Mar 09, 2024 ¦ 固定リンク
| かっちりつくる |
|
「かっちり」の類語や語彙をあらためて調べてみると ぴたっときちんと正しく正確に、堅く引き締まったさまを指すとのこと 奇を衒わずに「かっちり」つくる 設計の過程で出てくる数多の条件や問題点を正しく整理し 当たり前のことをしているだけなのに、当たり前に見えない そういう設計方法があるのだと思います  |
08:22, Saturday, Mar 09, 2024 ¦ 固定リンク
| 展覧会中止のお知らせ |
|
展覧会中止のお知らせ! 「感染急拡大に伴う福山市における対策強化」 の取り組みのため、ふくやま美術館が臨時休館になりました。 2日間開催の幻の展覧会になってしまいました。 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/199547.pdf |
19:06, Sunday, Aug 08, 2021 ¦ 固定リンク